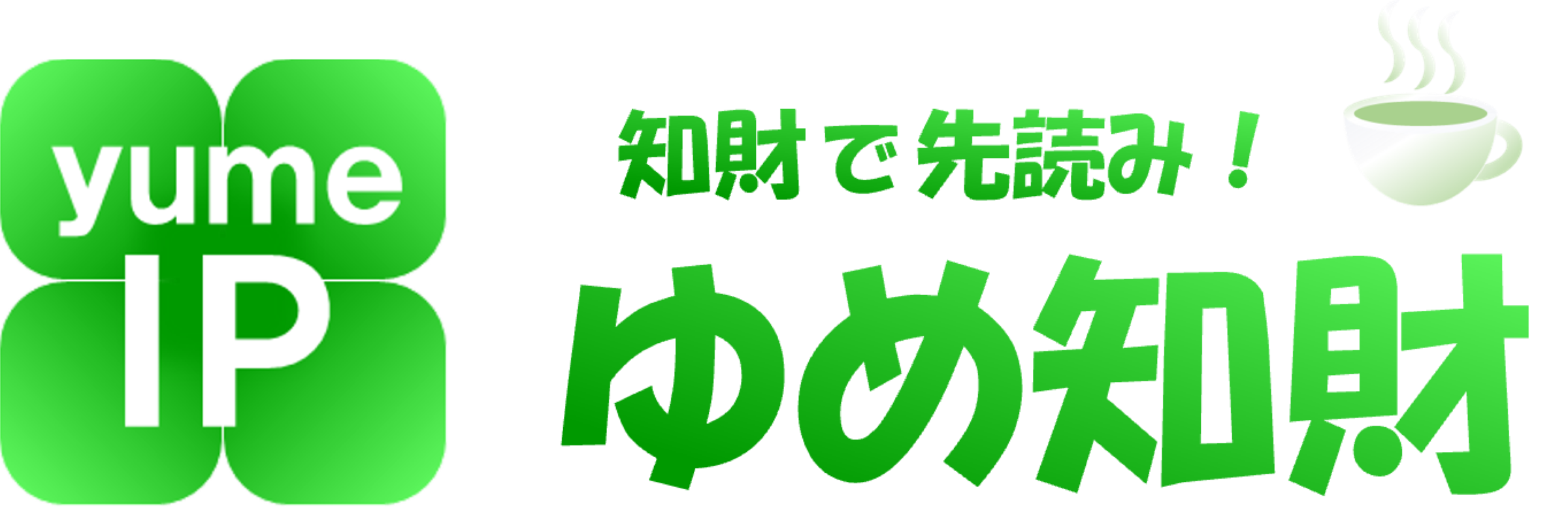標準必須特許をどのように考えるか?

JETROのニューヨーク事務所から少し前(2022年6月10日)に発信された「司法省等が2019のSEPの政策声明を撤回」というタイトルの記事が、少しだけ気になったので触れてみたいと思います。
改めて、SEPというのは、標準必須特許(Standard Essential Patent)の略称です。通信技術に関する機器や設備の仕様など、ある程度は共通にして誰でも使えるようにしておかないと不便な技術について、いわゆる「標準規格」として決まりを設けることがありますが、その標準規格に必ず使われる特許のことです。
誰でも使えるようにすることと、特許にするということは、お互いに矛盾した行為になります。開発した技術を一般に広めたい場合、技術を独占せずに開放してしまうのが良いですが、そうすると、せっかく開発した技術が他社にタダ乗りされて利益が得られない、そんな特許は出す気にならないという、ジレンマが発生します。
SEPは、その矛盾を解決するひとつの手段となり得ます。技術分野や業界ごとに標準規格を策定する組織が存在することが多いですが、その標準規格に関する特許(SEP)を指定すると共に、その組織に所属する会員企業に対しては、その特許を「公平、合理的かつ非差別的(Fair, Reasonable And Non-Discriminatory)な条件」(FRAND条件)でライセンスすることを求め、その見返りとして相当のライセンス料を約束する、といった仕組みです。
一方、技術分野や業界の境界を越えた取り組みが増加する中、何が適切なFRAND条件なのか、調整や合意がとても難しい場面が増えて来ています。SEP保有者、つまり「報酬を受け取る側」が有利になるか、SEP利用者、つまり「代償を支払う側」を有利に扱うか、各国の政策もその時々で揺れ動いています。
上記の記事では、米国司法省(DOJ)、米国特許商標庁(USPTO)、米国立標準技術研究所(NIST)の三機関が、2019年に出された”SEP保有者寄り”の声明、つまり、特許権者側を重視する政策を推進するとした声明を撤回した、という内容です。
それでは、逆に”SEP利用者寄り”、つまり、特許利用者側を重視して競争を促進するとの声明を出したかと言えば、そうではなく、声明を取り消しただけ、という状況です。
つまり、上記の三機関は、いったん中立の立場を取った、というのがこの記事の内容になっています。米国が揺れ動いている様が見て取れます。
特許がSEPに指定されると、仮に訴訟になった場合、通常の特許侵害訴訟とは異なり、特許権者がFRAND条件に従っていたか否かが、侵害有無の判断基準のひとつとされます。
つまり、特許権としては弱いものになってしまうと言えます。発明者または特許権者としては、特許権を弱めてもオープンな戦略を取るのか、強い特許権を確保してクローズな戦略を重視するのか、選択を迫られることになります。
こうしたことは、「モノからコト」という流れの中では、ますます重要な課題になります。筆者が馴染み深い化学業界では今のところ、あまり標準必須特許が問題になる状況は見られないのですが、技術の境界を越えたイノベーションが増える中、戦略として真剣に考えねばならない課題と言えます。