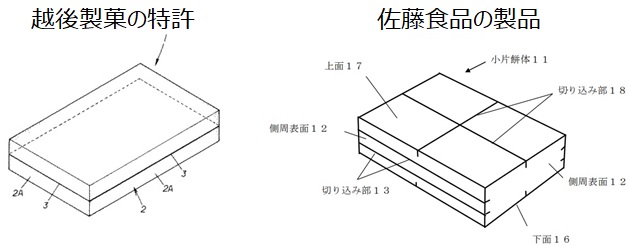「音」が商標になる?~「マツモトキヨシ」の事例より
日本において「音」を商標として認める制度改正があったのは2015年、最初に登録が認められたのは2017年になります。
インテル、久光製薬、大幸薬品など、有名企業が宣伝などで使っていた、誰もが聞いたことあるメロディが、次々と「音商標」として登録になりました。
それ以来、2025年1月時点で、音の登録商標は約370件。新たな形態の商標も、ようやく定着してきた感があります。
「マツモトキヨシ」の音商標
大手ドラッグストアの「マツモトキヨシ」も、響きの良いユニゾンによる男性の歌声、耳に残りやすい7つの音階によるメロディ、歯切れのよいリズムで構成された、音商標として登録しています。
「マツモトキヨシ」の音商標は拒絶されたことがある
しかし、この「マツモトキヨシ」の音商標は、特許庁からいちど、拒絶を食らっています。理由を要約すれば以下の通り。
- この商標は、音と”マツモトキヨシ”という言葉のセットだね。
- それじゃ、この言葉だけ分離して、見てみようか。
- ところで、「マツモトキヨシ」という人は、他にも居るよね。
- 他のマツモトキヨシさんからは、OKを貰ってる?ないよね。
- じゃあ、この商標は登録できないね。残念!(商標法4条1項8号)
これに対して、ドラッグストア「マツモトキヨシ」は、ガンガンに反論しています。すごく乱暴に要約すれば以下の通り。(勝手にマツキヨの気持ちになって書いてみました。)
- 氏名と言えば戸籍でしょ。戸籍の氏名は漢字でしょ。うちらはカタカナじゃん!
- 「マツモトキヨシ」と言えば、ドラッグストアのあの「マツモトキヨシ」に決まってんでしょ。うちら有名じゃん!
その反論を、特許庁は冷たく退けます。
- 漢字だろうがカタカナだろうが、氏名は氏名だよ。
- オタクがどれだけ有名だろうと、「マツモトキヨシ」が他人の氏名であることに変わりはないよね。
当然(?)、マツキヨはこれに納得しません。特許庁じゃラチがあかん、ということで、裁判所(知財高裁)に訴え出ました。
逆転勝訴!「マツモトキヨシ」の音商標が登録された顛末
すると一転、知財高裁は、ドラッグストア「マツモトキヨシ」の言い分を認めました。乱暴に要約すると以下の通り。(ちなみに、知財高裁は東京の裁判所です。)
- 実際問題、普通の人が、あの「マツモトキヨシ」という”音”を聞いて、「ああ、これはマツモトキヨシという”人の名前”やなあ」とか思うか?
- そんなことないやろ。あの「マツモトキヨシ」は、店の中でもコマーシャルでも流れてて、みんなに知られてたやん。
- あれ聞いたら誰でも、ドラッグストアの「マツモトキヨシ」と思うやろ。誰も他人の名前やとは思わへんで。
- 特許庁はん、もっぺん審判やり直してや。頼むで。
この最後の「頼むで」というのがミソ。要するに「登録にしたってや」ということ。
登録にするかどうかは、あくまで特許庁の権限。知財高裁は、特許庁の判断を「間違ってるから取り消す」としか言えないのが法律の建前。「登録が相当」とも言えません。
でも、「取り消す」といったら、「登録だ」と言ってるようなものですよね。法律や組織の縦割りは、実にマドロッコシイ・・・。
特許庁は普通、知財高裁の「頼むで」に逆らうことはしません。「やっぱり登録が正解でしたね」という結論を出します。
この「マツモトキヨシ」の音商標も、そうしてめでたく登録となった次第です。ドラッグストアの「マツモトキヨシ」さん、お疲れさまでした!
なぜ判断が覆ったか?音商標をどう捉えるべきか?
特許庁の判断が覆ったポイントは、音商標を構成する音(音楽的要素)と言葉(言語的要素)を分離して良いか否か、という点だと考えます。
今回、特許庁の新しい判断では、音商標は「言語的要素を音楽的要素に乗せてなる商標」という表現になっています。
特許庁は当初、「マツモトキヨシ」という言語的要素だけを切り離して判断しましたが、正しくは、言語的要素は音楽的要素と一体として判断せねばならない、ということになります。一般人の常識的な感覚に近い判断かな、と思います。
音商標の構成要素は、安易に切り離さず、一体として判断する。これが音商標を捉える標準的な考え方になるかと思われます。
ただ、知財高裁も「絶対に切り離したらアカン」とまでは言っておらず、どんな場合に切り離して良いか否かは、まだ議論の余地があるようです。
以上、今回は、「マツモトキヨシ」の音商標が登録になった経緯についてご紹介しました。
Views: 32